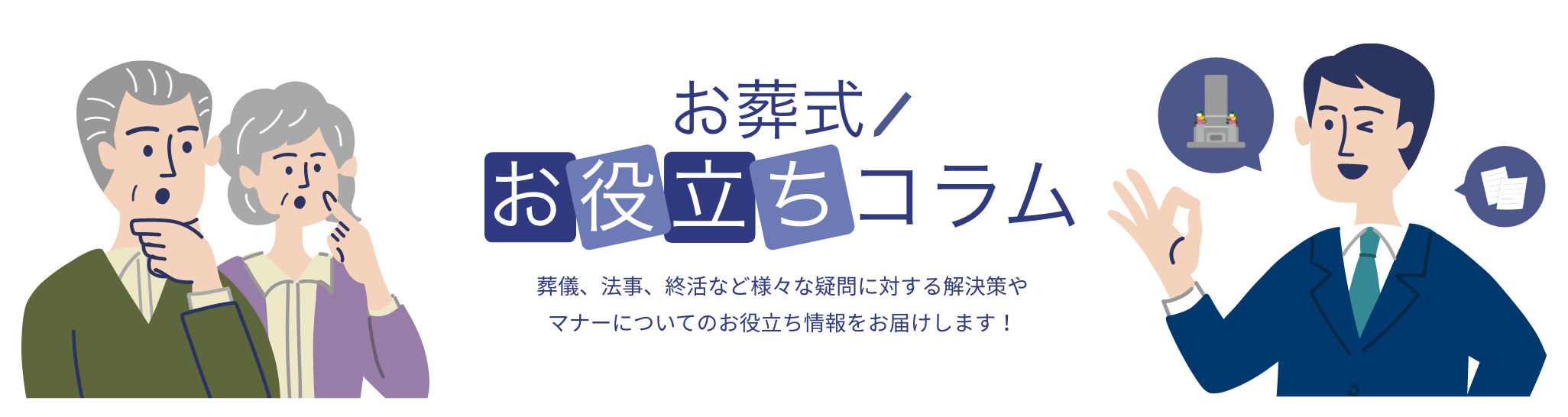葬祭費と埋葬料の違いとは?金額や申請方法などについて解説
2023.05.11
葬祭費(そうさいひ)と埋葬料(まいそうりょう)は、故人様が加入していた健康保険から支給される給付金です。どちらも故人様の葬儀を主催した方に対して支払われます。したがってご遺族は、健康保険からいくらかの補助を受け取ることが可能です。
葬儀には多額の費用が必要になるため、葬祭費と埋葬料を有効活用したいところでしょう。そこで今回は、葬祭費と埋葬料の違いや、金額、申請方法などを解説します。
葬祭費と埋葬料の違い

葬祭費と埋葬料は両者とも非常に似ているため、ご遺族が受け取れるのはどちらなのかを把握することが大切です。ここでは、葬祭費と埋葬料がそれぞれどのようなものか解説しつつ、両者の違いを判断するためのポイントをご紹介します。
葬祭費とは
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合に、葬儀を行った方が受け取れる給付金が葬祭費です。葬祭費を受け取るためには、故人様が住んでいた市区町村の役所に申請する必要があります。
埋葬料とは
健康保険や組合健保に加入していた方が亡くなった場合に、埋葬を行った方が受け取れる給付金が埋葬料です。埋葬料を受け取るためには、故人様が加入していた全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や、各種健康保険組合に申請する必要があります。
葬祭費と埋葬料を判断するポイント
葬祭費と埋葬料は非常に似ているものといえるため、両者の違いについて明確にしておきましょう。判断するポイントは、故人様の加入していた健康保険の種類です。
「国民健康保険(後期高齢者医療制度も含む)」に加入していた場合は葬祭費、その他の健康保険に加入していた場合は埋葬料となります。
|
葬祭費 |
埋葬料 |
|
・国民健康保険 ・後期高齢者医療制度 |
・協会けんぽ ・組合健保 ・共済組合 |
具体的な事例としては、葬祭費のうち国民健康保険に該当するのは、75歳未満の自営業・個人事業主・無職の方です。一方、後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者の方、また埋葬料のうち、協会けんぽや組合健保に該当するのは、会社員の方が対象です。共済組合に該当するのは、公務員の方が考えられます。
日本は「国民皆保険制度」の名の下に、すべての国民がいずれかの健康保険に加入しなくてはいけません。国民皆保険制度とは1961年にスタートした、いつでも誰もが必要な医療サービスが受けられることを目指した制度のことです。つまり、原則として日本国民であれば、葬祭費か埋葬料のどちらかを受け取れます。
被保険者本人ではなく扶養家族が亡くなった場合にも、同様に受け取ることが可能です。
葬祭費の金額と申請方法
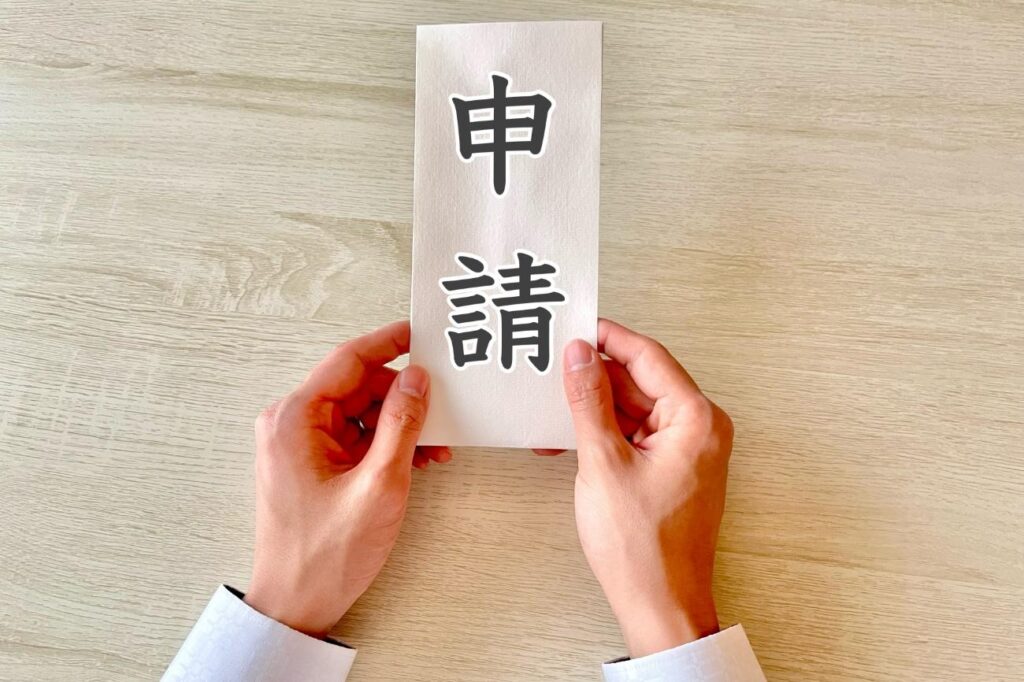
葬祭費の金額は、自治体によって異なります。多くの自治体(神奈川県全域もこれに該当)が5万円、東京23区は7万円です。
葬儀を行った方(喪主)が、各市区町村の役所窓口(保険年金課など)へ申請する必要があります。葬祭費の申請方法は、以下の通りです。
|
・保険証の返却、および資格喪失の手続きを行う(死亡後14日以内) ・葬祭費の申請を行う(葬儀日の翌日から2年以内)。 |
葬祭費の申請は、保険証の返却と同時に行うとスムーズでしょう。なお、申請場所と必要書類、記入書類は以下の通りです。
|
申請場所 |
故人様の住所地にある市区町村の役所窓口 |
|
必要書類 |
・保険証(未返却の場合) ・葬儀費用の領収書、または会葬礼状 ・申請者の身分証 ・申請者の印鑑 ・申請者の銀行口座番号の控え |
|
記入書類 |
国民健康保険葬祭費支給申請書、または後期高齢者医療葬祭費支給申請書 |
埋葬料の金額と申請方法

埋葬料の金額についてご紹介しつつ、埋葬料の細かい種類についても触れておきます。埋葬料の種類は、3つに分類されます。それぞれの内容を確認しておきましょう。
●埋葬料
| ・故人様:被保険者 ・受取人:埋葬を行った家族 扶養家族でなくとも、被保険者に生計を維持されていた場合は、これに該当 ・金額:5万円 |
●家族埋葬料
| ・故人様:被保険者の扶養家族 ・受取人:被保険者 ・金額:5万円 |
●埋葬費
| ・故人様:被保険者 ・受取人:埋葬を行った人(生計を一にする家族でない) ・金額:5万円の範囲内で、埋葬にかかった費用 |
いずれの場合も、埋葬を行った方が管轄の協会けんぽ支部、または健康保険組合に申請します。埋葬料の申請方法は、以下の通りです。
|
・保険証を速やかに会社へ返却 ・事業主が資格喪失届を提出 ・埋葬料の申請(死亡日の翌日から2年以内) |
埋葬料の申請は、会社が代行する場合もあるため確認しておきましょう。申請場所と必要書類、記入書類は以下の通りです。
|
申請場所 |
管轄の協会けんぽ支部、または健康保険組合 |
|
必要書類 |
保険証(未返却の場合) 事業主による死亡の証明 ※場合によっては、住民票や葬儀費用の領収書も必要 |
|
記入書類 |
健康保険埋葬料(費)支給申請書 |
葬儀費と埋葬料における3つの注意点

葬祭費と埋葬料について分かってきたところで、よくある質問で扱った事柄以外にも、三つのポイントを押さえておきましょう。
注意点1.健康保険の資格喪失後に埋葬料が適用されることがある
以下、いずれかの要件を満たす場合、会社を退職した後(健康保険の資格喪失後)であっても、埋葬料が適用されます。
| 1.被保険者が資格喪失後、3か月以内に亡くなったとき 2.被保険者が資格喪失後、傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている期間に亡くなったとき 3.被保険者が資格喪失後、傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けており、継続給付を受けなくなった日から3か月以内に亡くなったとき |
被保険者本人以外の扶養家族が亡くなった場合は、家族埋葬料を受け取れません。
また、葬祭費と埋葬料の両方は受け取れないため注意が必要です。例えば、協会けんぽに加入していた方が退職して国民健康保険に加入し、3か月以内に亡くなった場合、協会けんぽに埋葬料を申請します。この場合、葬祭費を二重で受け取ることはできません。
注意点2.直葬でも葬祭費は受け取れる
多くの自治体では、お見送りの形式に関わらず葬祭費を受け取ることが可能です。
近年、お通夜や葬儀を行わず、火葬のみで故人様を見送る直葬(火葬式)を執り行うご家庭が増えています。直葬を行った場合でも、基本的には葬祭費が受け取れることを覚えておきましょう。
ただし、自治体によっては、葬祭費を受け取れない可能性もあります。火葬のみのお見送りは「葬祭」にあたらないと判断される場合があるためです。
葬祭費をスムーズに受け取るためには、領収書の名目を「葬祭」であることを認識しやすくしたり、身内のみの葬儀であっても会葬礼状を作成したりする方法が考えられます。
注意点3.葬祭費にも埋葬料にも該当しない場合がある
ここまで、葬祭費と埋葬料について説明してきましたが、どちらにも該当しない場合も存在するため、いくつか事例を挙げておきます。
| ・労災がおりる場合 ・葬祭扶助を利用する場合 ・保険料が未納である場合 |
労働者が業務上の事故等を理由に亡くなった際には、労災保険から「葬祭料」が支給されます。そのため、葬祭費や埋葬料には該当しません。
葬祭扶助とは、故人様や喪主が生活保護を受けており葬儀費用の負担が困難な場合や、身寄りのない方の葬儀を第三者が行う場合に支給されるものです。生活保護制度の1つであり、上限は設けられている反面、葬儀にかかった費用を全額負担してもらえます。
ただし、お見送りの形式は、火葬のみ(直葬)に限られます。この場合、葬祭費や埋葬料には該当しません。
保険料が未納である場合、葬祭費を差し止めされることがあります。
葬祭費と埋葬料のよくある質問

最後に、葬祭費と埋葬料のよくある質問と回答をご紹介します。申請する前に、確認しておきましょう。
Q.申請しないと受け取れないのでしょうか?また、申請の期限はありますか?
A.はい、申請しないと受け取れません。申請期限については、葬祭費が葬儀日の翌日から2年以内、埋葬料が死亡日の翌日から2年以内です。
Q.支給申請書は前もって記入しておいたほうがよいですか?
A.組合や市区町村によって、書式が異なるため、特にその必要はありません。役所の窓口で、申請書を入手できます。
Q.申請から振込までにかかる期間はどのくらいですか?
A.約2か月です。申請した銀行口座に振込まれます。
Q.葬祭費の申請を行う役所はどこでも大丈夫ですか?
A.いいえ、故人様が住んでいた住所地の市区町村に限られます。
Q.葬祭費の場合、葬儀費用の領収書の提示が必要ですが、領収書の宛名になっている方(喪主)でなければ受け取れないのでしょうか?
A. 原則はそうです。ただし、申請書の委任状欄に記入することにより、領収書の宛名になっている方以外も受取人にできます。
Q.「埋葬にかかった費用」とはどこまでをさすのでしょうか?
A.火葬料や霊柩車代、僧侶への謝礼なども含みます。葬儀にかかった費用一式と認識してしまって問題無いでしょう。
まとめ

葬儀を行った際、健康保険から支給されるのが、葬祭費と埋葬料です。どちらに該当するかは、故人様が加入していた保険の種類によって決まります。葬祭費と埋葬料は、申請しなければ受け取れません。ただし、詳しい申請方法については、保険組合や役所へ確認しておく必要があります。
横浜市や川崎市で葬儀を行う際には、実績豊富なお葬式の杉浦本店にご相談ください。横浜市、川崎市における多くの葬儀実績があります故人様やご家族、ご親族の気持ちに寄り添った葬儀プランをご提案いたします。
葬儀費や埋葬料についてのご相談も承りますので、24時間365日いつでもお気軽にお問い合わせください。